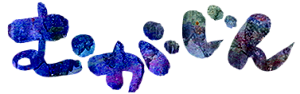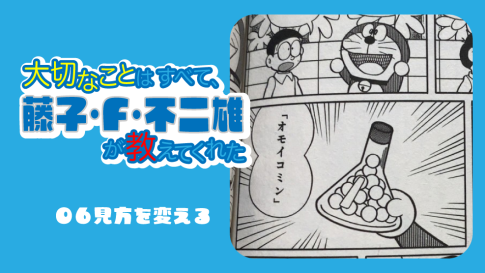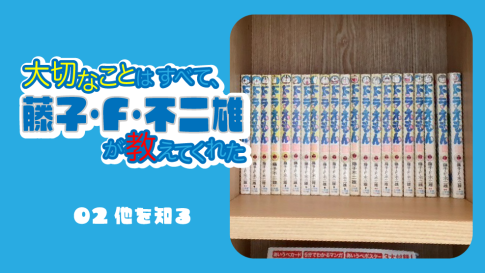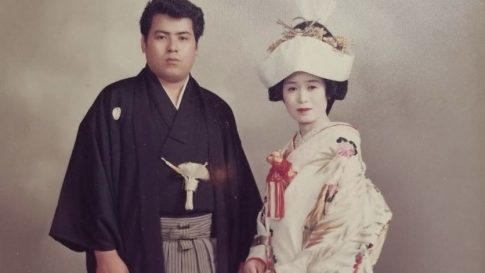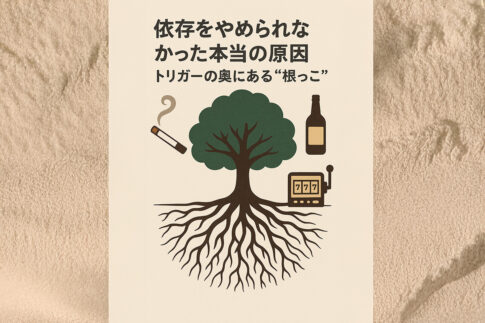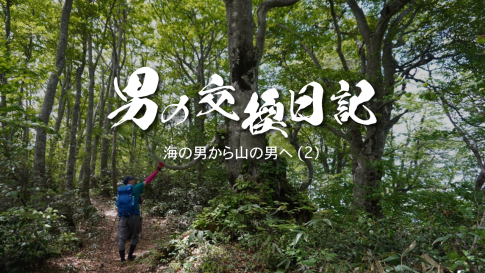前編では、筆者がタバコや酒の依存をやめられた体験をお話しした。多くの場合、こうしたものは「デメリットが大きい」と直感した瞬間に、自然と手放せることがある。
でも、ギャンブルのように「頭では危ないと分かっていてもつい手を出してしまうもの」は、表面的な行動を変えるだけでは抜け出せないこともある。
後編では、筆者自身のギャンブル依存体験を通して、「なぜやめられなかったのか」「どうやって抜け出せたのか」をより深く掘り下げていきたい。
ギャンブル編1:“お金が無い”は真実か?
依存症研究では、ストレスや退屈、誘いなど「ハイリスク状況」が行動のトリガーになるとされる。筆者の場合、ギャンブルの最大のトリガーは「お金が無い」という思い込みだった。
収入が入って余裕が出た時も、支払いに追われて財布が空になった時も、「このままでは足りない」「もっと増やさなければ」という焦りがスイッチとなり、ギャンブルへ向かってしまった。勝っても負けても、それが都合よく“次への理由”に変わる。
では「お金が無い」とは何を意味するのか。
――欲しいものを今すぐ買えない、食べたいものを今すぐ食べられない。つまり、自分の欲求を満たせない状況だ。外食や趣味にお金を使えないことも、その一部だった。
掘り下げていくと、この感覚は幼少期の体験に根があった。詳細は書けないが、施設で1人だけ叱られた経験がトラウマとなっていた。当時の感情を思い出すと涙が出ることもある。
しかし、執着していたことが心から消えると、完了した瞬間に「あれ、なんだったっけ?」と思うことが多い。

ギャンブル編2:トリガーと“根っこ”
さらになぜ?という問いを繰り返して深掘りすると、ギャンブルをする自分を「だらしない」と思う感覚も出てきた。根気強く深層心理に向き合うことで、少しずつ執着は消えていく。
“お金が無い”という思い込みが薄れていくと、手持ちが数千円しかなくてもあまり関心を持たなくなった。欲しいものがあっても給料が入ったら買えばいいと思えるようになった。
以前は、給料が入ったばかりでもすぐに使い切って、次の給料日まであと2週間あるのに手持ちはこれくらい……と焦り、最終的には「ギャンブルで増やせばいい」と考えていた。
恐ろしいことに、お金が無いという不安は、実際にお金が無くなる現実を引き寄せることが多い。人生はあなたの思った通りになるというが、それはポジティブなことでもネガティブなことでも同じだから気をつけて欲しい。
実際のところ、ギャンブルで負けた後はいつも「今日負けた◯万円があれば、あれもこれも買えたし支払いもできたのに……」という後悔が押し寄せるが時すでに遅し。
世の中には、筆者のようにお金が無いことで脳の処理能力が落ちる人が一定数いるそうだ。しかし、根気強く自分と向き合うことで、「もうお金の心配をしなくていいや」と自然に思える瞬間が訪れた。
自分を縛り付ける不安の縄を解いたことで、筆者はついにギャンブルを手放せた。お金が欲しくてたまらない気持ちが無くなると、自分でも驚くほどにギャンブルをしたい気持ちが起こらなくなった。

学術的アプローチとその限界
依存に関しては、多くの研究が行われてきた。
- 再発防止モデル(Marlatt & Gordon, 1985):トリガー回避と対処行動を重視
- General Theory of Addiction(Jacobs, 1986):依存は孤独や不安からの逃避として機能する
- Pathways Model(Blaszczynski & Nower, 2002):依存に至るタイプ別のトリガーを説明
これらの理論は依存についての理解を助けるが、いずれも「行動を変えること」に焦点を当てている。だが、筆者にとってはそれだけでは不十分だった。
根っこが残っている限り、環境や状況次第で依存はいつでも再燃してしまうからだ。大谷サーンの通訳だった頃に7億をギャンブルで溶かした一平くんも、彼自身の根っこをどうにかできない限り一生苦しむことになるだろう。
Reboot™️というアプローチ
ほりたみわ(現・多神和)が提唱する「掘り下げと抽出」という考え方は、現在Reboot™️というプログラムとして体系化されている。
Reboot™️は、表面的な行動ではなく、「なぜそのトリガーに反応するのか」に注目する。掘り下げて根っこの感情や思い込みを見つけ出し、それを手放していくのだ。
根っこ自体はすぐには消えない。しかし、「これはもう今の自分には不要だ」と理解できると、同じ状況に直面しても以前のようには揺さぶられなくなる。
学者の理論は依存の理解を助けるが、いずれも『行動を変えること』に焦点を当てている。意志の力には限界がある。筆者のように我慢が効かない人間は、まず自分と向き合うことが大事だ。
「やめなきゃいけない」と考えるのではなく、なぜやってしまうのか──その根本原因を見つめるのだ。

まとめ
酒やタバコは「デメリットが大きい」と直感したときに自然と手放すことができた。
特に、タバコをやめられた体験は「依存は我慢ではなく、自然と不要になる瞬間がある」という実感を教えてくれた。その感覚が酒をやめる支えにもなった。
一方でギャンブル依存は、表面的なトリガーを避けるだけでは抜け出せなかった。
「お金が無い」ことに対して焦りを覚える自分の反応と、その奥に眠る根っこを見つけたとき、ようやく行動を変えて依存から抜けることができた。
学術研究は依存の全体像や再発の仕組みを理解するうえで強い助けとなる。しかし本当に自由になるためには、その理論を超えて自分自身の根っこに光を当てていく作業が不可欠だと感じている。
依存から抜け出したいと願うなら、我慢ではなく根っこを探してみてほしい。なぜそのトリガーに反応するのか、その奥にどんな思い込みや感情が潜んでいるのか。
その答えに気づいたとき、行動は自然と変わり、どうしてもやめられなかったアレコレは“不要なもの”へと変わっていくはずだ。