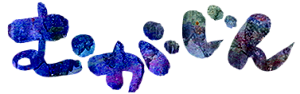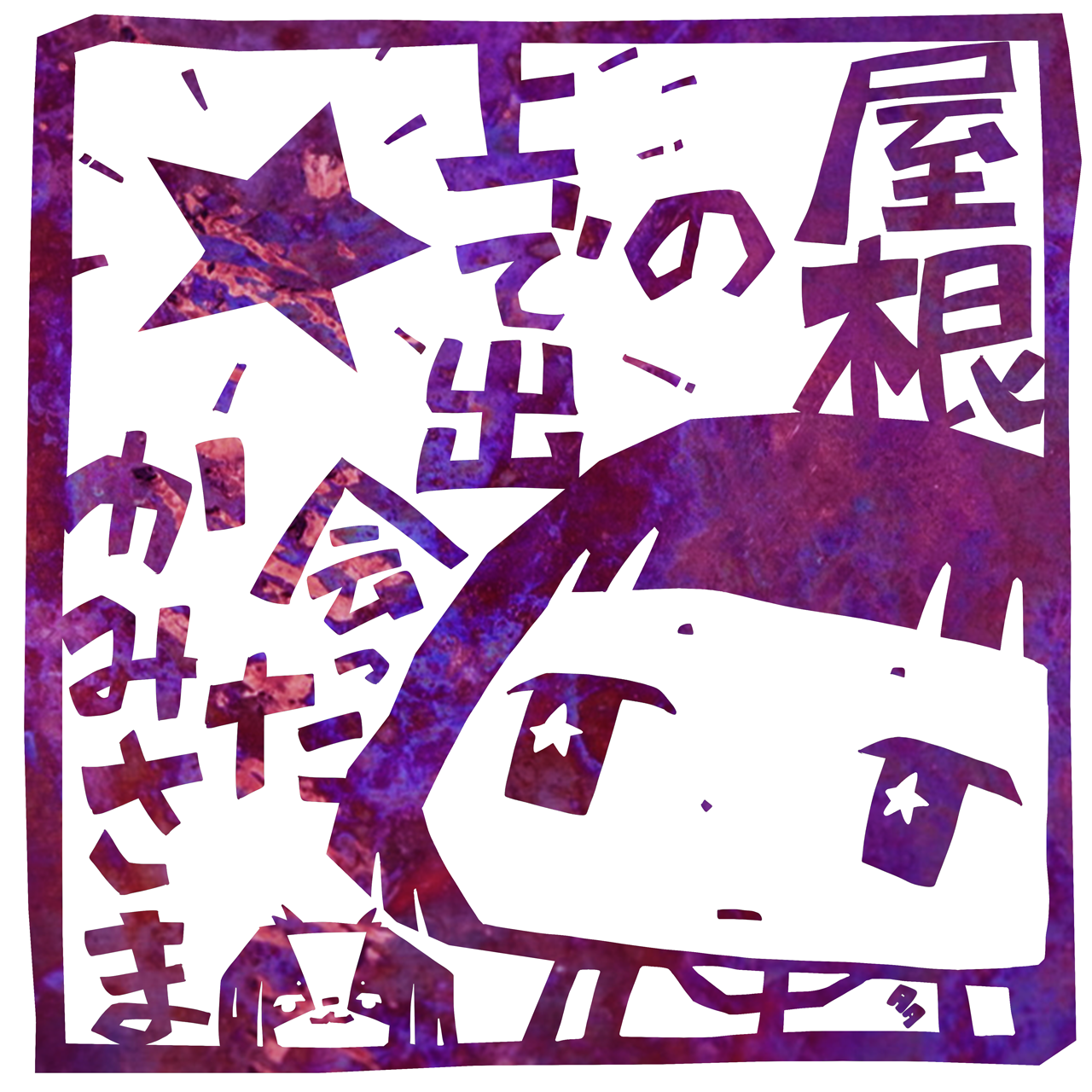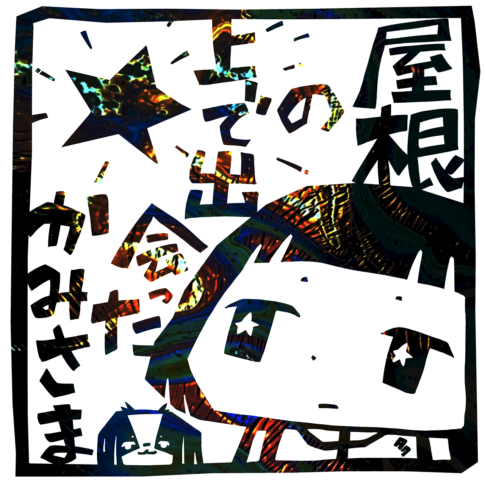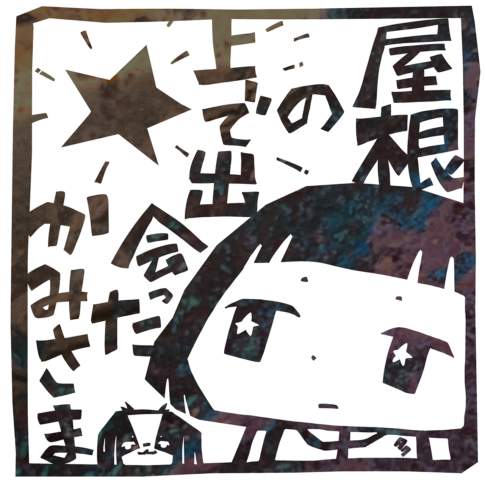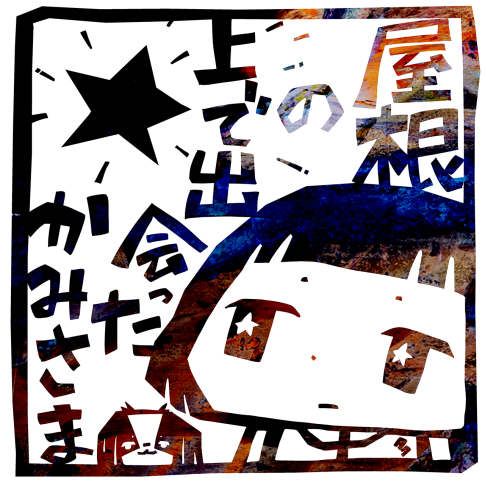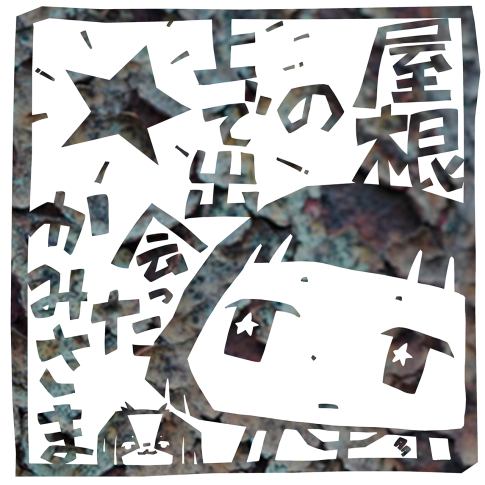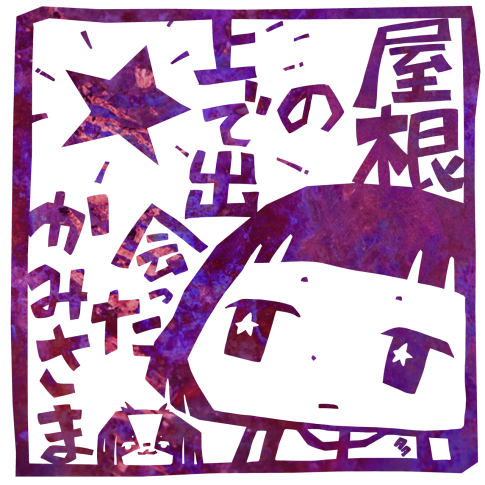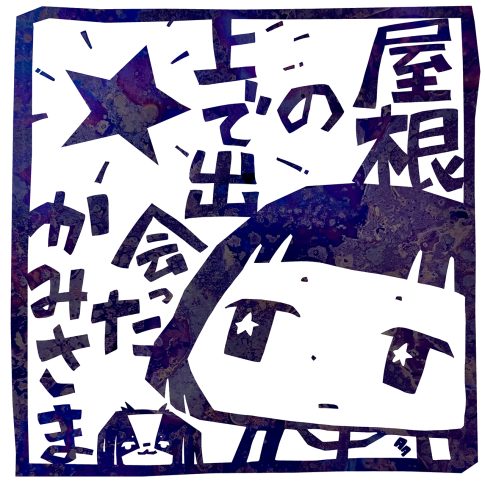——かみさまが、右上から消えた日々
憧れていたのは「大学生活」
大学に入ったら、フォルクローレとか登山系っぽいハイカラな名前のサークル(名前忘れた)とかに入って、週末はみんなで合宿して、おそろいのパーカー着て、恋とかしてるんだと思っていた。
そういうのが、「大学生活」ってもんだと勝手に思っていたし、わたくしには絶対にないものだったからこそ、ちょっとだけ憧れていたの。
でも、入学してみたら、どう考えてもそっち側には行けなかった。
わたくしは陽キャではなかったし、今も陽キャではない。あの輪の中には、どうがんばっても入れなかったんです。
そんなわたくしが、唯一心からわくわくしたのが、麻雀でした。
小学生の頃からずっと、PCの麻雀ゲームをひとりで打っていたけれど、実際に人と卓を囲むなんてことは、一度もなかった。あ、いや、正確には高校時代に少しだけあったけれど、あれはカウントしないでおく。
だから、「麻雀」の文字をホワイトボードに見つけたとき、全身が「これだ!!」ってなったの。
あと、こっそり気になったのがそこの近くに描かれていたソーセージの絵と燻製部の文字。「燻そうぜ!」みたいなことも書かれていたような気もするけど、ちょっとあまりに訳がわからなすぎてそっとしておいたんですよ。
そんなわけでわたくしが入ったのは、どう考えても「憧れの大学生活」とはほど遠い麻雀サークルでした。でもずっと人と打ちたかったし、これが自分なんだからしゃーない。
ジャンマットとメスティンとけーた
初めて行った麻雀サークルの部屋でわたくしが見たのは、おそらく垂木とベニヤで組まれたであろう、お手製の台の上にジャンマットが置かれている光景。
そこではもさっとした男たちが卓を囲みジャラジャラしていた。もちろん麻雀牌を。
なんというか、ちゃんとしてないのが最高だった。もさっとした男たちに即入部(入サークル?)の意思を表明し、あっという間にメンバーになったのでした。
ちゃんと受け止めてくれたのはもさっとした中でも、いや、中にいたからイケメン枠に見えたのか、ロン毛のさわやか風モサメン。
そして気づけば毎日通うようになったある日。
卓の上にキャンプ用のガスバーナーを置き、アルミのメスティンでお湯を沸かしている男がいたんです。
それがけーたでした。
きゅん。
今思えば「なんでそこできゅんってするの」って自分にツッコミたいけれど、でもあの瞬間、ジャンマットとメスティンとけーたは、ひとつの芸術だったの。
しかもけーたはそこで沸いたお湯と、フィルムケースに入れたインスタントコーヒーをカップに入れて、優雅にコーヒーを味わい始めちゃったりして。
そんな恋の始まり……にも気づいてなかったくらいの頃。
わたくしが呼吸できた輪
麻雀サークルのメンバーは、ダンナ、中(あたる……この人がイケメン風モサメン)、成田(メガネ)、鈴木(これまたメガネ)、そしてけーた(これまたまたメガネ)。
この「メガネの輪」の中で、わたくしはようやく呼吸ができるような気がしてたの。えぇ、もちろんわたくしもメガネ。
みんなで卓を囲んでいたある日、誰からか燻製の話が出まして。
そこでわかったこと。あのホワイトボードに描かれていた燻製部のソーセージの絵――じつはけーたが描いたものだったんです。
「あの絵描いたのけーただったんだ……」
わたくしはなんだか運命めいたものを感じながら、ゆるやかに、でも確かにけーたに惹かれていったのでした。
嘘をつけない恋の終わり
大学に入ったばかりの頃、わたくしにはイーノという恋人がいた。中学時代の同級生。
高校では離れ離れになったけれど、まだその頃は付き合ってるってわけでもなくて。だけど週に一度は電話をくれていて、そのうち毎週の電話が楽しみになって。大学で東京に出てきたとき、ようやく恋人同士になった人。
でも、本格的に大学生活が始まってから、会う時間はどんどん減っていった。そしてある日、イーノはわたくしに言ったのです。
「麻雀と俺、どっち取るの?」
わたくしは、答えられませんでした。というか、答える必要があるとも思わなかったの。だから正直に言った。
「そんなのわかんない」
イーノは言った。
「なんで嘘でも俺って言えないんだよ」
わたくしの好かれるようで嫌われるところでもある正直さ。いえ、ばか正直。
「だって嘘つきたくないんだもん」
それから、イーノとの関係はふわりと終わったのでした。
泣くこともなかったけれど、確かに一枚、皮がはがれたような感じがあった大学1年生の夏の前。
写真と手と洗濯機と、結婚
あれよあれよと仲良くなったけーたとわたくしは、いつの間にか同棲するようになっていた。家に洗濯機がなくて、ふたりでコインランドリーに通っておりました。
「結婚したら、お祝いに洗濯機もらえるらしいよ」
それが結婚のきっかけ。今でも信じられない話だけど、本当にそうだった。
けーたは料理が上手かったし、写真もすごくよかったの。
高校時代、写真部の部長だったわたくしは「この大学には日本一大きい暗室がある」と聞いてこの学校を選んだのでした。確かに大きい暗室ではあったけれど、日本一は本当だったのか……。
けーたはそこで現像をしていた。わたくしは暗室で現像する楽しみを高校で知って、大学でさらに楽しくなるかと思っていたらそうでもなかった。
でも撮る楽しみは変わってなかったし、むしろ増した。大好きな人を写真に収めたいという気持ちがむくむくしてたから。
だけど、けーたは自分の“顔”を撮られるのがとても苦手だったの。
だから、許されたのは“手”だけ。
おかげでわたくしは、けーたの手ばかりをモノクロで撮る日々。いい手がたくさん撮れました。
かみさまは、右上から消えていた
その頃のわたくしには、「かみさま」はおりませんでした。
子どものころ、ずっと右上にいたかみさまは、けーたといるあいだ、たぶん完全に姿を消しておりました。
いなかった、というより、わたくしが、見なくなっていた。
かみさまはずっといたんです。
でもわたくしの視界から、完全に外れていた。
何度か声をかけようとしたのかもしれないけれど、もうそのときのわたくしには、右上を見る余裕がなかったの。