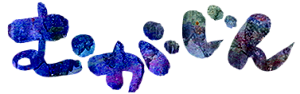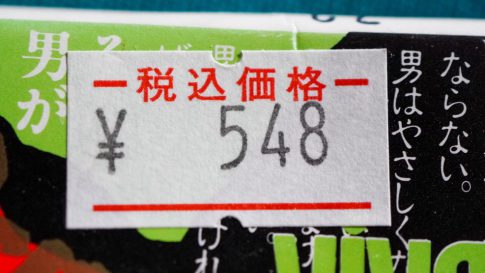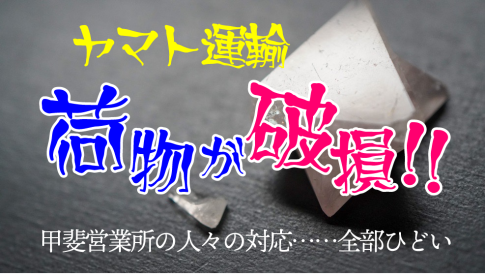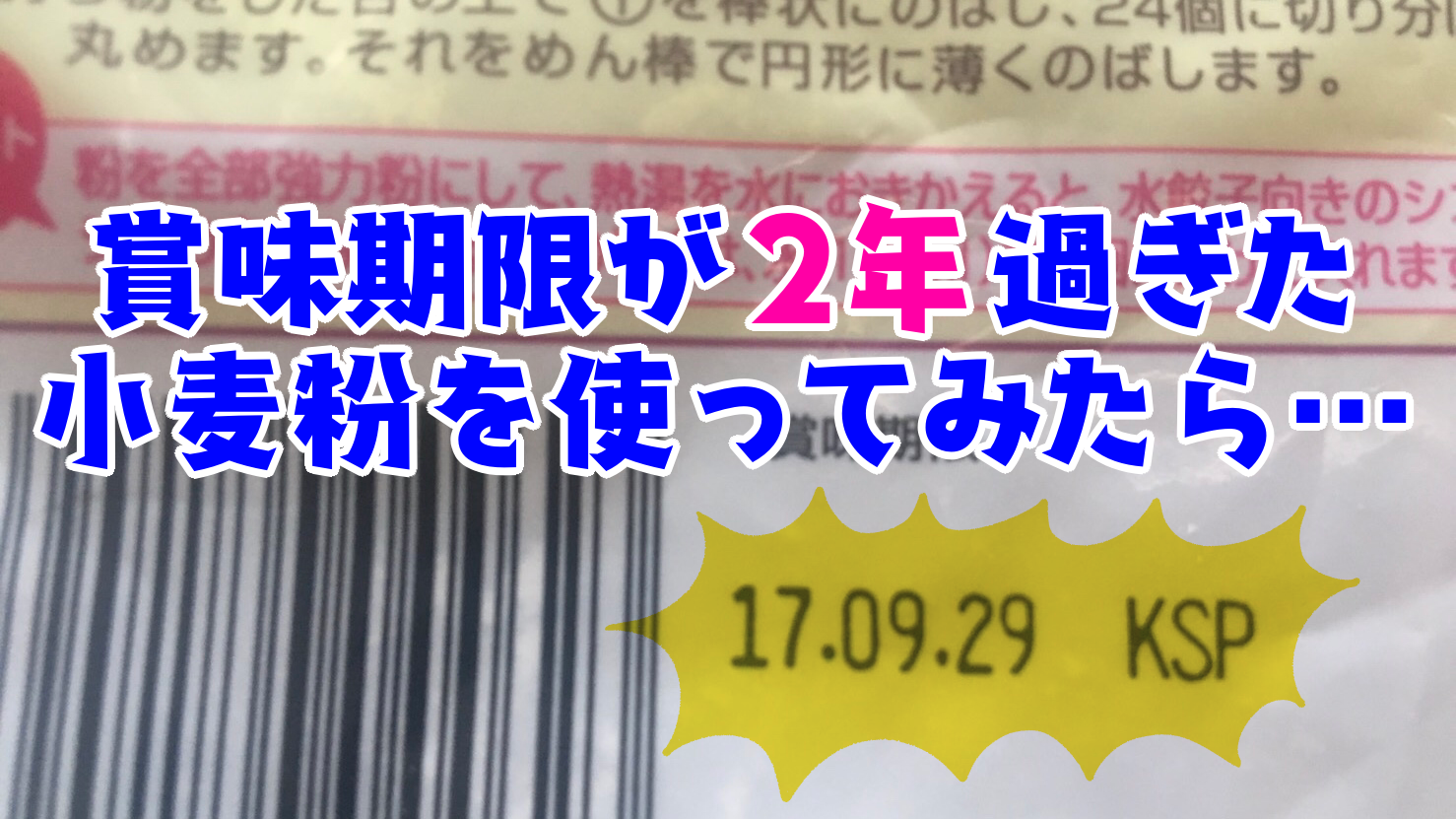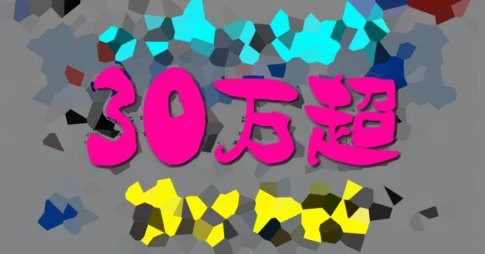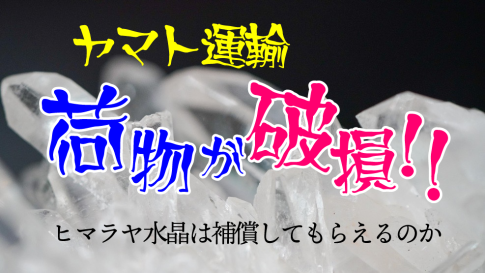NHK連続テレビ小説「ばけばけ」第1週(1)「ブシムスメ、ウラメシ」を見た。
小泉八雲の妻セツこと、松野トキさんが主役のこのドラマ。
小泉八雲こと、レフカダ・ヘブンに物語を語るシーンから始まる。
まさか朝っぱらからこんなにも「うらめしや」という言葉を聞くとは思わなかった。おまけに、丑の刻参りだろうか、白装束を来た人が藁人形に釘を打ち付けるシーンも。
朝ドラといえば爽やかな朝の象徴……そのイメージが初回からあっさり覆される。
いいぞ、もっとやれ。
うらめしやって何?
そういえば、うらめしやって何なんだろうか?いつからあるの?ふと気になった。
恨むという漢字が使われるということはなんとなく分かるけど……。
調べてみると「うらめしや」は、実は古い言葉で、江戸時代からもう存在していたらしい。
語源はシンプルで、「恨めしい」+感嘆の「や」。
つまり「ああ、恨めしいことよ」という、残された者の嘆きや無念をそのまま吐き出す言葉だ。
恨みつらみをドラマチックにひと声で表す、なんとも情緒的な響きである。
江戸から朝ドラへ――「うらめしや」のルーツをたどる
この言葉が“幽霊の決めゼリフ”として広まったのが江戸時代。
歌舞伎や浄瑠璃、怪談芝居で亡霊が登場する際、「う〜ら〜め〜し〜や〜……」と、ゆったりした節回しで現れる演出が観客をゾクッとさせた。
四谷怪談のお岩さんを筆頭に、舞台での「うらめしや」は
怖いけれどどこか艶っぽく、観る者の心を掴んで離さなかったという。
現代では、もはや幽霊を表す記号のようなものになっているが、
もともとは人の心が持つ“未練”や“愛着”を語る言葉。
ドラマ「ばけばけ」の登場人物が口にするその響きを聞くと、
単なるホラーを超えて、人が人を想い続ける切なさまで感じ取れてしまう。
朝から怪談、でも人間くさい物語
そんなこんなで朝ドラらしからぬ“朝から怪談”の幕開けでした「ばけばけ」。
阿佐ヶ谷姉妹が声を担当する蛇と蛙のキャラクターが登場して、ポップで不思議な世界にもなっている。
小泉八雲記念館で八雲とセツの生涯を知った者からすると、ドラマで描かれるであろう人生の苦労や葛藤が自然と頭をよぎる。
それでも、この人間くさい「うらめしや」があるからこそ、物語はただの幽霊話には終わらない。
この余韻を胸に、朝のテレビ前でじっくり見守りたくなる気分だ。