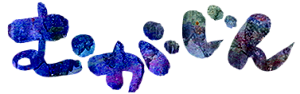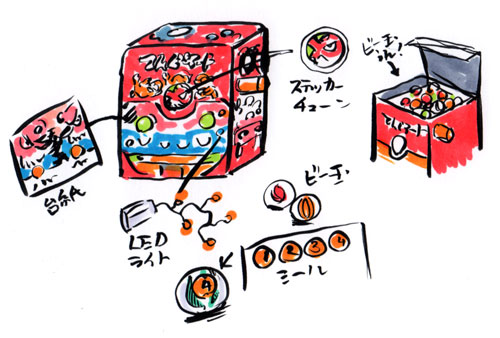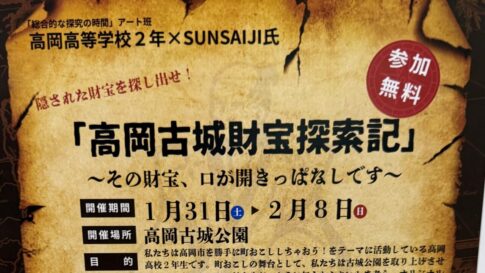さて、むがじん展が始まって1週間が経とうという頃になってようやく自己紹介です。
むがじん展ではチューリップの写真や、万葉集にちなんだ草花を撮った作品を展示しています。




英語好きから写真好きに
写真家の冨田実布(とみたみほ)です。東京都出身、平成元年生まれ。
宝塚歌劇に魅了され写真の世界を志しました。20歳の時に「カメラの使い方も分からないけどカメラマンになりたい」と周りに言いまくっていたら、たまたま「るるぶ」という旅行誌などを扱う編集部を紹介されました。
「じゃあカメラマンの人に聞いてあげるから、その人から教わりなさい」と社長が言ってプロを紹介してくださり、この世界に足を踏み入れました。
夢が叶った後、表現について考えた
私の師匠は会社員を1〜2年やって独学でカメラマンになった人でした。「俺には行けない写真の世界がある、そういう世界へ君は行け。俺みたいに何でも撮れるカメラマンにはなるな」と言ってくれたのを覚えています。
写真家として芸術の道を意識するようになったのは、あの時の師匠の言葉があったからだと思います。当時の自分にはその意味もよく分からないままでしたが。
宝塚歌劇の舞台をはじめ、帝国劇場、青山劇場、東京ドーム、代々木国立競技場などさまざまなステージに通い、雑誌やウェブサイトに写真を掲載してもらう夢のような日々。
大好きなスターさんの退団までを撮ることができて、23歳くらいでいったん目標達成。「あれ、この後どうしよう?」という状態に陥りました。
20代は「本当にやりたいことは何なのか」を常に模索。そうこうしているうちに、2018年頃から表現力を上げるための勉強を始めました。
とにかく本を読み、映画やドラマを観て感動した瞬間を分析し、感じたことを言葉にしていこうと。
むがじんに記事を書くようになり、自分の文章力の無さに気づきましたが、写真をやる上でも文章の読解力が大切だと思い、書くことや言葉での表現にも力を入れ始めます。
閑話休題:宇多田ヒカルと小袋成彬の音楽が芸術を教えてくれた
不思議に思われるかもしれませんが、私にとって芸術を強く意識したのは他でも無い音楽でした。特に、宇多田ヒカルと小袋成彬という2人のアーティストが、私の感性を刺激して、創作のイマジネーションをくれています。
宇多田ヒカルが「この人を世に出さないといけない」と初めてプロデュースしたのが小袋成彬という人物で、彼がデビューしたのが2018年でした。
「純文学のよう」なんて言われたデビューアルバムは、音以上に訴えかけるものがありました。
彼らの曲を流しながら花を撮るときは、花との波長がさらに合う気がします。
チューリップが教えてくれたこと
2020年、友人の死が引き金となり「生死」というテーマを見つめ始め、2023年にチューリップと出会いました。
チューリップが枯れた姿の衝撃と、枯れてもなお一層の輝きを見せる姿に魅了されました。その話はこちらからどうぞ。


『ぬばたま』:自分の「色」を出すために
芸術には疎いのですが、物心ついた時には宗教画を見ることが好きな子供でした。ミケランジェロ、ダヴィンチ、カラバッジョなどが印象に残っています。
自分にとっての芸術の下地みたいなものは唯一そういったものの記憶の名残かもしれません。
その自分が好きだった西洋絵画の世界観を出そうと工夫したのが、実はこの「ぬばたま」という作品です。

「ぬばたま」は万葉集ではおなじみの草花。ヒオウギという花の種子を指し、その黒々とした光沢のある様は「黒」や「闇」、「夜」などの枕詞に使われたのだとか。

高岡市に移住してから万葉集に縁ある場所だと知り、万葉集なんてよく分からないなと思っていたのですが、高校生の頃に百人一首にハマっていたことを思い出しました。
熱心に百人一首を覚えて、校内の大会にも出ていたと母に言われるまですっかり忘れていたから不思議です。それでも、枕詞を目にするとうろ覚えながら歌が出てくるんです。
これがキッカケとなり、万葉集に出てくる草花をテーマにした写真作品を撮りはじめました。
花との対話で見えてくるもの
花を撮るコツは何かと問われれば、「対話すること」と答えます。
全てに通じることですが、とにかくよく観察することが大切です。すると、だんだんと花が教えてくれるような気がします。
「今、撮らなきゃいけない」
そう思った瞬間の勘というのはよく当たるもので、明日でいいかと思った時はもうダメなんです。最期の輝きを見逃さないように、そしてレンズを通して私が見た美しさを表現するために共に短い時を過ごしています。
以前、枯れた花を撮っていると話したら、わざと花を枯れさせているかのように思われたことがあります。枯れるのを待つのではないんです。
私にとっては一緒に過ごした時間がちゃんとあるんです。だから水をあげずに枯れさせることはしないし、別れ難いから最期に輝く瞬間を撮っています。
死を見つめることで今を精一杯生きることができる
2022年、5カ月間だけですが葬儀の現場に派遣バイトで行っていました。大人になってから経験した友人の葬儀に立ち会って、とても興味が湧いたのです。
私の親が亡くなる時は、自分の最期の時は、一体どのような気持ちになるのか。物心つく前からずっと気になっていました。リハーサルはないし、人生で一度きり。
その瞬間になるまでどんなものか分からないのが死というもの。私にとっては、おそらく生まれてからずっと死が最大の関心事なのだと、心のどこかで確信していました。
「終わりを見つめることから始める」というのは、私が大好きな「7つの習慣」にも出てくる言葉です。
自分がどのような終わりを迎えるかは分かりませんが、どんな終わりを迎えたいのかを考えたら、そこまでの道を思い描くことができると思います。
死を意識することは私にとっては希望であり、いたずらに恐怖におびえることもなく、必ず迎える今の自分の肉体が滅びることに向き合えるんです。
おわりに
むがじんとは、無我夢中な人生を生きる人たちが、自身の無我夢中なことについてその情熱を伝える媒体です。その熱が伝播していくことで世の中の人たちが知らなかった世界を覗くキッカケとなり、また新たな熱が生まれるかもしれない。
世の中にもっと無我夢中になって好きなことをやる人たちが増えたらいいなと思います。ぜひ一度むがじん展に足をお運びください!